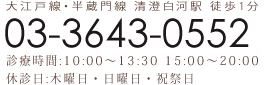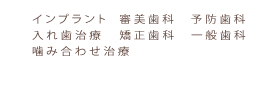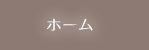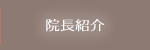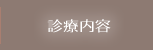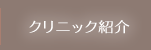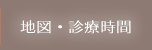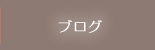加齢や歯磨きの癖で進む“歯ぐきの後退”と対策
鏡を見たときに
「なんだか歯が長くなった気がする」
「歯ぐきが下がって、根元が目立つ」
そんな違和感を覚えることはありませんか?
その症状は、歯肉退縮(しにくたいしゅく)と呼ばれ、
放置すると知覚過敏や虫歯、歯周病悪化につながることがあります。
今回は、清澄白河の歯医者さん「にしざわ歯科クリニック」が、
歯肉退縮の原因・症状・対策についてわかりやすく解説します。
歯肉退縮(しにくたいしゅく)とは
歯を支えている歯ぐきが下がり、歯の根元(歯根)が露出してくる状態をいいます。
見た目の変化だけでなく、歯の寿命に関わる重要なサインでもあります。
歯の根元はエナメル質よりも弱い象牙質で構成されているため、
露出すると虫歯になりやすく、冷たいものがしみる症状も現れやすくなります。
歯肉退縮の主な原因
歯ぐきが下がる原因は1つではなく、生活習慣や加齢、歯周病などが複雑に関係します。
① 歯周病による組織の破壊
歯周病菌が歯ぐきや骨をゆっくり破壊し、歯ぐきの位置が下がってしまいます。
自覚症状が乏しいため、気づいたときには進んでいることも多い病気です。
② 強すぎるブラッシング
硬い歯ブラシや力任せの磨き方は、歯ぐきにダメージを与えます。
特に“横磨き”の癖がある方は要注意。
長年の摩擦で歯ぐきが後退することがあります。
③ 加齢による自然な変化
年齢とともに皮膚や粘膜が衰えるように、歯ぐきも薄く・弱くなります。
中高年以降で歯肉退縮が増えるのはこのためです。
④ 噛み合わせ・歯ぎしり
強い力が特定の歯にかかると、歯周組織に負担がかかり、歯ぐきが下がりやすくなります。
⑤ 口腔習癖(くうこうしゅうへき)
・歯を強く当てる癖(TCH)
・頬杖
・舌の押し付け
こうした小さな癖が、長期的には歯肉の位置に影響することがあります。
歯肉退縮が進むとどうなる?
見た目の変化だけでなく、次のようなトラブルが起こりやすくなります。
・冷たいもの・甘いものがしみる(知覚過敏)
・歯の根元の虫歯(根面う蝕)が増える
・歯周病が進行しやすくなる
・歯が長く見え、老けた印象になる
・歯が揺れやすくなる
特に、根元の虫歯は気づきにくく進行も早いため注意が必要です。
歯肉退縮の対策
歯ぐきは一度下がると、基本的に自然に元に戻ることはありません。
しかし、進行を止めたり見た目を改善したりする方法はあります。
● 正しいブラッシング習慣を身につける
・力任せではなく、ペンを持つような軽い力で
・毛先のやわらかい歯ブラシを使用
・歯ぐきと歯の境目を小刻みに優しく磨く
ブラッシング1つで、退縮の進行を大きく防ぐことができます。
● 歯周病の治療・定期検診
歯肉退縮の背景に歯周病がある場合、治療が不可欠です。
歯石除去やクリーニングで炎症をコントロールし、進行を止めます。
● 知覚過敏・根面虫歯の予防
・フッ素入り歯磨き粉
・知覚過敏用の薬剤塗布
・象牙質コーティング
これらで歯の根元を守ることができます。
● 噛み合わせ・歯ぎしりの改善
ナイトガード(マウスピース)を使用して、歯や歯ぐきへの負担を減らします。
● 歯肉移植(審美的改善)
審美性が大きく損なわれている場合や、知覚過敏が強い場合には、
歯ぐきを移植する「歯肉移植術」で改善することもできます。
日常生活でできる予防の工夫
歯肉退縮は日々の習慣で大きく変わります。
・口呼吸ではなく鼻呼吸を意識する
・頬杖や歯を当てる癖をやめる
・歯ブラシを頻繁に交換する(1か月に1本が目安)
・歯間ケア(フロス・歯間ブラシ)を取り入れる
小さな積み重ねが歯ぐきの健康を守ります。
まとめ
・歯肉退縮は、歯ぐきが下がることで歯の根元が露出する状態
・原因は歯周病・強いブラッシング・加齢・歯ぎしり・癖など多様
・進行すると知覚過敏・根面虫歯・見た目の悪化につながる
・正しい歯磨き・歯周病治療・噛み合わせ管理で進行を防げる
・必要に応じて歯肉移植で改善することも可能
歯ぐきが下がった気がする…と感じたらにしざわ歯科クリニックへご相談ください
歯肉退縮は、早めに気づけば進行を止められる症状です。
見た目の改善だけでなく、歯を長く守るためにも、
気になるサインがあればお気軽にご相談ください。
2025年11月25日 カテゴリ:未分類