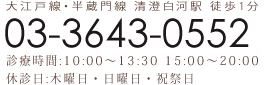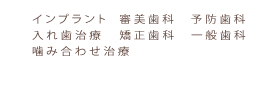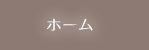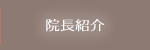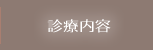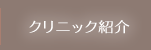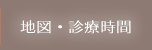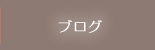皆さんは「バイオフィルム」という言葉を聞いたことがありますか? 歯磨きを怠ると歯の表面がヌルヌルとした感触になることを経験された方は多いでしょう。実はそのヌルヌルの正体こそが「バイオフィルム」なのです。そして、このバイオフィルムこそが、日本人が歯を失う原因の第一位である「歯周病」の、まさに元凶とも言える存在なのです。
バイオフィルムとは何か?
バイオフィルムとは、微生物が作り出す集合体であり、特定の表面に付着して形成される粘性の膜のことです。簡単に言えば、細菌たちが身を守るためにバリアを張って集団で生活している状態、とイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。
台所の排水溝や、お風呂場のヌメリを想像してみてください。あのヌルヌルも、実はバイオフィルムの一種です。歯科領域においては、このバイオフィルムが歯の表面や歯周ポケットの中に形成されます。特に、歯と歯茎の境目や、歯間部、そして詰め物や被せ物の周囲など、磨き残しが多い部分に形成されやすい傾向があります。
このバイオフィルムの中には、数百種類もの細菌が生息していると言われています。それぞれの細菌が協力し合い、栄養を共有し、老廃物を排出しながら、強固なコミュニティを形成しているのです。
バイオフィルムが歯周病を引き起こすメカニズム
では、このバイオフィルムがどのようにして歯周病を引き起こすのでしょうか。そのメカニズムは以下の通りです。
細菌の温床となる: バイオフィルムは、歯周病を引き起こす「歯周病原性細菌」にとって格好の住処となります。これらの細菌はバイオフィルムの中で増殖し、数を増やしていきます。
毒素の産生: バイオフィルム内の細菌は、増殖する過程で様々な有害物質(毒素)を産生します。これらの毒素は歯茎に炎症を引き起こし、歯周病の初期症状である歯肉炎を発症させます。
免疫反応の誘発: 歯茎は、細菌の毒素から体を守ろうと免疫反応を起こします。しかし、慢性的にバイオフィルムが存在し続けると、この免疫反応が過剰になり、自身の組織(歯槽骨など)を破壊してしまうことがあります。これが歯周病の進行メカニズムです。
物理的除去の困難さ: バイオフィルムは非常に強固な構造をしており、うがいだけでは洗い流すことができません。また、通常の歯磨きでも完全に除去することは困難です。これが、歯周病が進行しやすい大きな理由の一つです。
歯肉炎の段階では、歯茎の腫れや出血が見られます。しかし、痛みがないことが多いため、自覚症状がないまま放置されがちです。バイオフィルムが除去されないまま放置されると、炎症はさらに深部へと進行し、歯を支える歯槽骨が溶かされていきます。歯槽骨が失われると、最終的には歯がグラグラになり、抜歯せざるを得ない状況に陥ってしまうのです。
バイオフィルムと全身疾患
さらに近年では、お口の中のバイオフィルムが、歯周病だけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼすことが明らかになってきています。バイオフィルムから放出された細菌やその毒素が血管を通じて全身に広がり、糖尿病、心臓病、脳卒中、誤嚥性肺炎など、様々な全身疾患のリスクを高めることが指摘されています。
特筆すべきは糖尿病との関係です。歯周病が糖尿病を悪化させ、逆に糖尿病が歯周病を悪化させるという、悪循環の関係があることが分かっています。つまり、お口の中のバイオフィルムをコントロールすることは、全身の健康を守ることにも繋がるのです。
バイオフィルムを除去し、歯周病を予防するには
では、この厄介なバイオフィルムをどのように除去し、歯周病を予防すれば良いのでしょうか。
毎日の丁寧な歯磨き(セルフケア): 歯周病予防の基本は、やはり毎日の歯磨きです。しかし、ただ磨くだけでは不十分です。歯ブラシの毛先を歯と歯茎の境目にしっかりと当て、小刻みに動かす「バス法」など、適切な磨き方を習得することが重要です。また、歯ブラシだけでは届かない歯間部や、歯周ポケットの入り口に存在するバイオフィルムを除去するために、デンタルフロスや歯間ブラシの併用が不可欠です。
歯科医院での専門的クリーニング(プロフェッショナルケア): ご自宅でのセルフケアだけでは、完全にバイオフィルムを除去することは非常に困難です。特に歯周ポケットの奥深くや、歯石の付着したバイオフィルムは、歯科医院での専門的なクリーニング(PMTC:プロフェッショナル・メカニカル・トゥース・クリーニング)によって除去する必要があります。PMTCでは、歯科衛生士が専用の器具を用いて、歯に強固に付着したバイオフィルムや歯石を徹底的に除去します。これにより、お口の中の細菌数を減らし、歯周病の進行を抑制することができます。
定期的な歯科検診: 歯周病は、自覚症状が少ないまま進行する病気です。そのため、定期的に歯科医院を受診し、お口の状態をチェックしてもらうことが非常に重要です。歯科医師や歯科衛生士は、歯周ポケットの深さの測定、歯茎の炎症状態の確認、レントゲン撮影などを行い、歯周病の早期発見・早期治療に繋げます。また、定期検診時にPMTCを受けることで、常に清潔な口腔環境を維持することができます。
まとめ
バイオフィルムは、歯周病の発生と進行に深く関わる「見えない敵」です。しかし、その正体を知り、適切なセルフケアとプロフェッショナルケアを組み合わせることで、私たちはバイオフィルムの脅威からお口と全身の健康を守ることができます。
歯周病は、一度進行すると元の状態に戻すのが難しい病気です。痛みがないからといって放置せず、日頃から丁寧な歯磨きを心がけ、定期的に歯科医院を受診して、お口の健康を積極的に守っていきましょう。
気になる症状がある方はもちろん、症状がなくても「最近歯医者に行っていないな」という方も、ぜひ一度、当院にご相談ください。皆様のお口の健康をサポートできるよう、スタッフ一同、誠心誠意お手伝いさせていただきます。